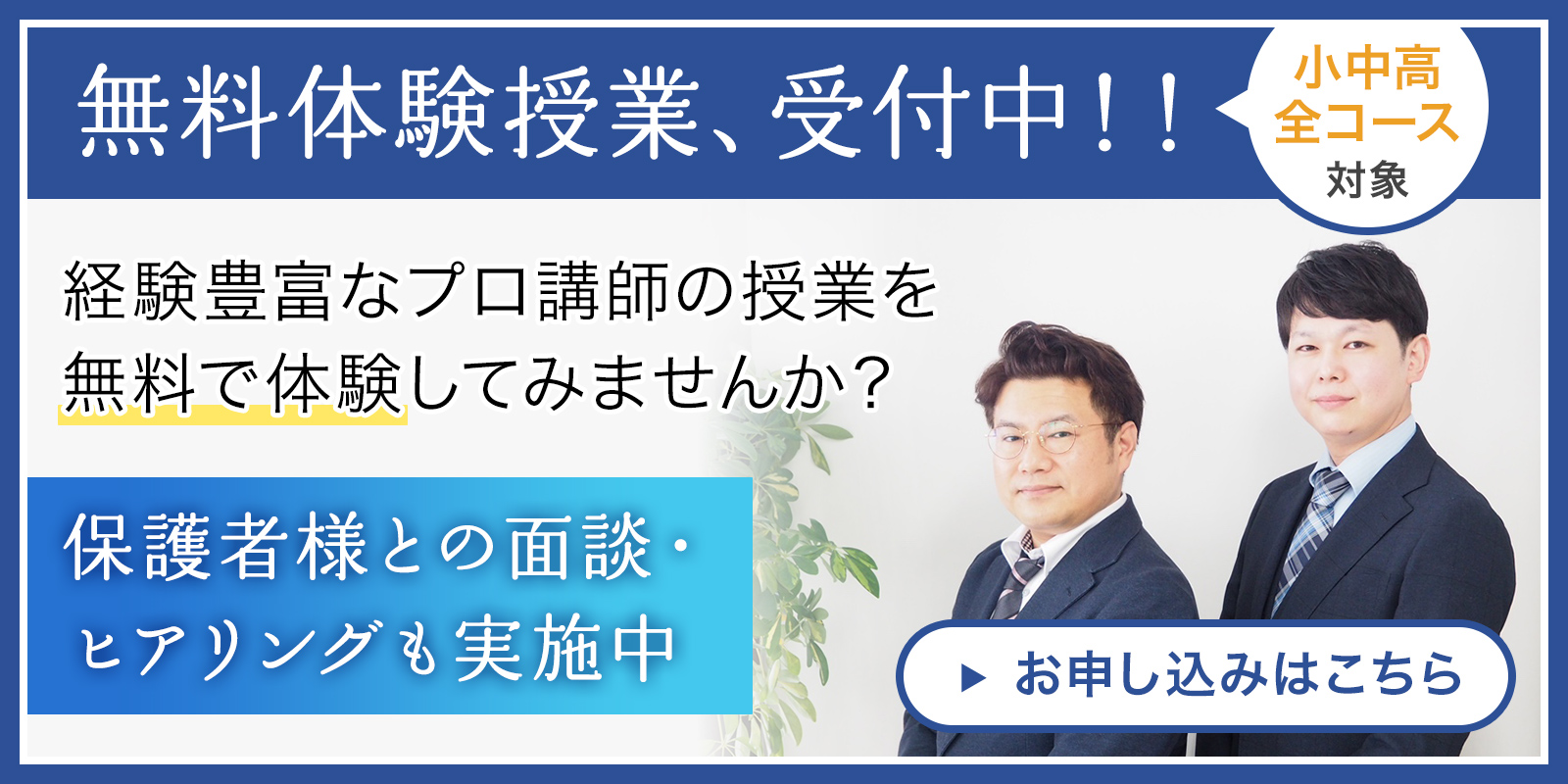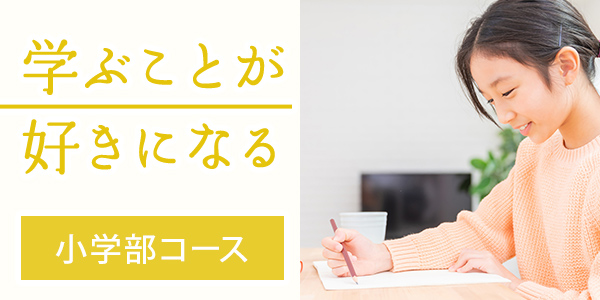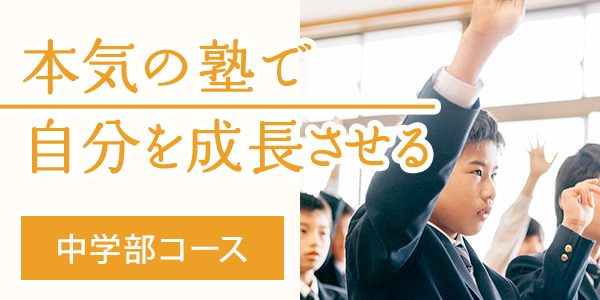今日の小学5年生算数の授業では「速さ」の単元に入りました!
「単位量あたりの大きさ」「平均」ときて、いよいよ「速さ」。
そしてこの後の「割合」と、小学校算数の最重要単元が続きます。
ここをしっかりと理解できているかどうかが
数学の得意・不得意を決めると言っても過言ではありません。
重要なのは、
速さの3公式をしっかり暗記させること・・・ではありません。
公式の意味を考えずに暗記だけすると
○時速「80km」を「道のり」と考え、「『速さ』がわからない?」となる
○単位が揃っていないのに、そのまま当てはめて計算してしまう
こんな感じで、「速さの問題苦手~」となってしまいがちです。
学習塾プルーフでこの単元を教える際に気を付けていることは3点。
1つ目は、子ども達は時速、分速、秒速という言葉を理解するのに時間がかかるということ。
「時速40kmってどういうこと?」と問いかけて、
「1時間あると40km先まで進めるってこと!」といった感じで説明できない場合、黄色信号です。
プルーフの授業では問題の度に、しつこいくらい言い換えます。
「15分間に27kmとぶ鳥の分速は?」
→「15分間に24kmとぶ鳥は1分でどれだけ進んでる?」
「時速98kmで走る列車が3時間に進む道のりは?」
→「1時間あると98km進む列車は3時間あるとどこまで進む?」
「時速40kmで走る自動車が120km進むのにかかる時間は?」
→「1時間あると40km進む自動車は120km進むのに何時間かかる?」
あくまでも前に習った「単位量あたりの大きさ」の続きであることを
強く意識させていくのです。
2つ目は、単元の導入では計算は思い切って省き、立式に集中させること。
授業中は「式を言ってくれれば、計算は先生がやるよ!」と伝えています。
そして出てきた数字の意味を考える方に集中する。
子ども達は「計算が早いこと」を「算数ができる」と思いがちです。
「分速240mで12分進むと何m?」といった問題を240と12しか見ずに、
計算しやすいからというだけで「240÷12=20で20m!」
と言ってしまったりします。
算数・数学は計算よりも、目的に応じた立式と出た数字の解釈が肝となります。
小5の算数が数学の得意・不得意を決める、というのは
「単位量あたりの大きさ」からが「立式と解釈」が重要となるからです。
3つ目に、数量を体感的にイメージさせることです。
家から学校まで900mあります。毎日時速3.6kmで歩いて登校しています。
何分かかりますか?
といった問題を単位を換算せずに計算して
250分!や250時間!、あるいは250m!とか250km!と答えてしまう。
実際にその数量をイメージさせてみれば常識的にありえないことに気づくのですが、
公式だけ暗記して単純作業のように当てはめて計算しているとやってしまいがちです。
体育の授業で50m走は何秒だった?という話から
秒速〇mをイメージしてみたり、
自分の全速力と動物の走る速さや乗り物の速さと比較してみたり、
100m走やマラソンの世界記録をもとに出してみたり。
それを繰り返していくことで数量イメージを体得していくのです。
「具体から抽象へ」というのは学習の基本。
体感的に納得できるものは理解も早く、その理解をもとに
ゆくゆくは目に見えないもの、あるいは現実には存在しないものも
考えられるようになっていきます。
といった感じで授業を進めていますが、
もちろん、生徒一人ひとり理解の速さには差があります。
そのため、ここから繰り返し何度も何度も授業を行っていきます。
「単位量あたりの大きさ」「平均」「速さ」「割合」
中学でのつまづきの原因は小5のこれらの単元にあり!
余裕のある小学生の内に繰り返し繰り返し勉強していきます。
※実は小6も塾ではほぼ小学内容を終えているため、
次はこの単元の復習をメインに進めていきます。
こんな感じで進めている学習塾プルーフの授業ですが、
ご興味がございましたら、ぜひ体験授業へお越しください!
お問い合わせお待ちしています。